警備員指導教育責任者2号業務
刑法
◎警備業務と犯罪
- 「事故」の中には、窃盗、傷害、不法侵入その他の犯罪によるものが含まれ、警備業務に従事する警備員は、これらの犯罪の発生に接する機会が一般人と比べて多くなるものと思われる。
- 刑法についての知識がないと、誤認逮捕を行ったり、正当防衛が成立しなかったり、第三者に無用の負担をかけるなど、不適切な警備業務が行われることになる。
◎刑罰法規と罪刑法定主義
○刑法とは
実質的意義
- どういう行為が犯罪となり、それにどの程度の刑罰が科せられるものかという、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規律する刑罰法規の全てを意味する。
形式的意義
- 「刑法」という名の付けられた現行の法律そのもの、つまり刑法典を意味する。
○罪刑法定主義
- 犯罪が成立し、刑に処するためには、あらかじめ法律で、定めておく必要がある。
- 「このような行為をした場合は犯罪となる」「その場合このような刑に処する」ということ。
- 犯罪と刑罰をあらかじめ法律で定めておいてはじめて刑罰権行使ができる。
- 罪刑法定主義とは
- 犯罪と刑罰は法令で定められているべきという主義である。
○罪刑法定主義から派生して生まれる原理
- 慣習刑法の排斥
- 法律として、成立していない国民の常識や地元の風習など慣習を根拠に刑罰を与える事を禁止。
- 刑罰法規の不遡及
- ある行為をした当時は犯罪として規定されていなかった行為を、後から法律作りさかのぼってその行為を処罰することはできない。
- 類推解釈の禁止
- 「あるAという行為が犯罪なんだから、それに似たBという行為も犯罪である」といった犯人に不利な類推解釈によって罰する事は禁止する。
- 絶対的不定期刑の禁止
- 刑罰を言い渡す際に、刑期を全く定めないもの(無期とは別物)はダメである。
- 明確性の原則
- 通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合にその行為が刑罰を受けるものかどうかが読み取れなくてはならない。
- 実体的デュープロセスの理論
- デュープロセスとは、何人も法の定める適正な手続きによらなければ、生命・自由または財産を奪われないとする原則。
- 定めめられた手続きにしたがって裁判を行い、法律で定められている罪を科さなければならない。必要以上に重たい罪にしてはいけない、あくまでも犯罪との均衡を失しない程度の刑罰が課されなければならない。
(/_;)
警備員に、ここまでの内容が必要なのだろうか。。。
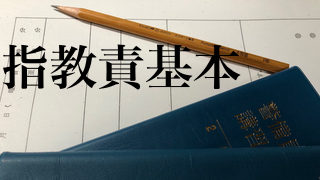


コメント