雑踏警備業務2級検定項目
(令和版)
第3章 雑踏の整理に関すること
第3節 人の誘導その他の雑踏の整理を行うため必要な事項に関する専門的 な知識
1 群集の性格と群集心理の特性
⑴ 群集の性格
-
人は誰しも、群集の中に入ると特別な心理状態になってしまう。
- 人は群集となった場合、個々人である場合とは異なった心理状態に左右され、思わぬ行動に出ることがある。
- 群集の中には指揮者がなく、秩序付ける組織もないため、些細な事案をきっかけにして、群集心理の赴くままに収拾できない事態に発展する場合も多くある。
○群集の三つの特性(性格)
- 付和雷同
- 付和雷同とは、自分の主義主張を持たず、深く考えずに他人の意見に同調すること。
- 群集の中に居ることによって、周りの人の非常識な行動になんの不自然さも感じず自らもそれと同じ行動を起こしてしまう。
- 群集心理に左右されて個々の理性を失うこと等が非常に顕著になってくる。
- 自己本位
- 群集を構成する一人ひとりに「我れ先に」という極めて強い「自己本位」の本能が先立ち、秩序のないところに一層混乱を生じさせる。
- 興奮状態
- 群集の中に居ることによって、感情が単純で非常に興奮しやすくなり、極端にかたよった行動を取りやすくなる。
- 混乱の中から、特有な心理状態を生み、当初予想もしなかったような興奮状態を引き起こす。
◯ 雑踏事故の一例
1. 第32回明石市民夏まつり花火大会
- 平成13(2001)年 7 月 21 日(土) 午後8時45分ごろから50分過ぎ
- 会場の大蔵海岸とJR朝霧駅を直結する明石市道朝霧歩道橋上で,超高密度群集滞留下での群集雪崩による転倒で犠牲者11人,負傷者248人の雑踏事故が発生した。
- 事故発生場所では群集密度13人/㎡~15人/㎡と推定されている。
- 帰路群集と来場群集が継続して流入する群集の累積による加重密度現象により滞留群集が超高過密度化し超高密度群集滞留が形成された。
- 群集密度13人/㎡~15人/㎡の群集内では,数回の「人津波」(群集波動現象)が発生し,恐怖心から個人と集団による危機回避行動(パニック)が発生した。
- 主催者側、警備会社側、警察署側の三者において、綿密な事前準備を欠いていた、その結果、事故発生現場での主催者、警察、警備会社等の初期対応の遅れ、連携不備及び指揮命令の一元化がなされず、さらに救急隊と通信指令室及び消防と受入医療機関等との情報通信の混乱が生じ、迅速かつ適切な救急対応が遅れた。
参考
- 兵庫県警察ホームページ(https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/index2.htm)
- 雑踏警備の手引き(https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/zattou/index.htm)
2. ドイツデュイスプルク Love Parade
- ダンス・ミュージックを中心とした世界最大級の野外音楽イベント
- 2010年7月、ドイツ・デュイスブルクで開催されたLove Paradeの会場アクセス道路で、入場群集と退場群集が交錯対向流として正面衝突状態で滞留し、超高密度群集滞留下での複雑な限界群集波動現象に起因して転倒と圧迫により犠牲者 21人、負傷者 500人強の雑踏事故が発生した。
- 会場への直接アクセス道路は、2か所に限定され群集誘導道路である誘導道路は、閉鎖的な地下道トンネルに合流しており群集流動のボトルネックとなっていた。雑踏事故はこの会場アクセス道路を中心に発生した。
3. 神戸ルミナリエ
- 1995年12月、阪神淡路大震災の犠牲者の鎮魂等を目的として、市街地道路で光の回廊神戸ルミナリエが開催された。
- 第1回神戸ルミナリエの来場者予測は11日間で76万人であったのに対して実際は254万人であった。
- 本事例は一方向流で発生した高密度群集滞留である。
- 道路を来場者に開放した当初は概ね密度5人/m²であったが、周辺からの来場者の継続流入によりルミナリエ通り入口に近い場所から順に群集の高密度化し、次第に道路一面に滞留(密度8人〜9人/m²)が拡大した。
- 群集滞留が、概ね密度8人/ m²で滞留幅が拡大すると前方群集の集団と後方群集が2分割される形で群集内で交互に左右に20cm〜60cm程度揺れる群集波動現象が発生し、密度が高くなれば波動幅が拡大する現象が確認された。
◎ 雑踏事故に連動する可能性の高い群集現象を明らかとするために必要な用語の定義
「高密度群集滞留」
- 発生した群集滞留に後続群集が継続流入することにより,概ね群集密度8人/㎡に高密度化した群集滞留を
「超高密度群集滞留」
- 更に,後続群集が継続流入して群集密度10人/㎡以上に高密度化し,雑踏事故に至る可能性が高くなる群集滞留
「群集波動現象」
- 高密度群集滞留の群集内で発生する群集密度及び群集圧力の分布の差異に起因する群集の「揺れ」現象
「限界群集波動現象」
- 密度10人/㎡以上の超高密度群集滞留の群集内では、生命の危険に対する恐怖心から集団と個人による危機回避行動に起因して発生する複雑な揺れ。
参考文献
- 地域安全学会ホームページ(http://isss.jp.net/)
- 雑踏事故に至る高密度群集滞留下での群集波動現象に関する研究
- -大規模イベント事例分析を通じてー (地域安全学会論文集 No.17, 2012.71)
- (http://isss.jp.net/isss-site/wp-content/uploads/2013/08/2012-004_cd.pdf)
⑵ 群集心理の特性
群集には次のような心理が働く。
- 分類方法は参考にする文献により色々あります、今回は特別講習教本による六つの分類です、一部指教責過去記事参照しています。
- 無名性
- 群集は、共通の対象への関心が高まることにより、その対象を中心として一つの全体的なまとまりとなり、次第に自己意識が薄らぎ、全体の中に融合してしまう。
- その結果、自己を無名の人として、また群集の一部分として意識するようになる。
- 無責任性
- 自己を群集の一部として自覚することから、結果に対する責任感が弱まる。
- 罰せられるような悪いことをしているのは、群集を扇動している者やこれに準じる者であり、その他の者は罰を免れることができる等の意識が生じ、罪悪感が薄くなり、責任性がなくなる。
- 無批判性
- 共通の対象に対する知識が部分的であるため、自分自身では正しい判断ができず、批判をすることなく他人の判断や発言を鵜呑みにするようになる。
- 情意性
- 互いに思うこと、考えていることが通じ合うこと。
- 知的作用が著しく後退し、これに代わって感情が強く表出する。
- この傾向は、人がその感情を他の人に伝達し表現することにより、さらに強まる。
- 雑踏という環境の変化によって、近道本能(社会的規範によらず、直ちに結果の発生を求める本能)にかえり、自分本位となって警察官等に従わない等、直情的な行動をとってしまう。
- 暗示性
- 意識の範囲が狭くなり、外部からの影響に対する抵抗が弱くなるため、暗示にかかりやすくなる。
- いつもならもっと冷静な人なのに誰かの意見に簡単に乗ってしまったり、その場の雰囲気にしたがった行動をしてしまう。
- 大きな声や、はっきりとした号令、命令につい従ってしまい、他の人の思いがまるで伝染するように、共通した考えや感情を持ちやすくなる。
- 親近性
- 群集の中にあるお互いの共通点や共通の興味の対象を通じて、親近感・同志感を持つようになる。
関連問題
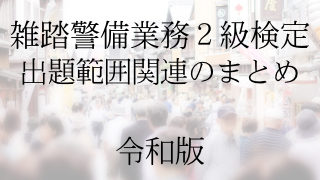

コメント