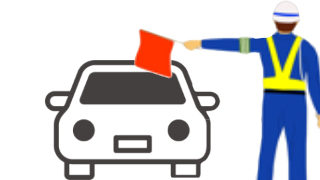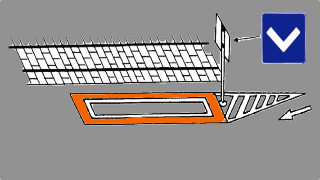道路交通法
道路交通法 良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書13
警察庁から、良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する中間報告書(令和5年12月良好な自転車交通秩序を実現させるための方策に関する有識者検討会)が発表されています。 今後、交通誘導警備業務、雑踏警備業務の実施現場にて、自転車に対する誘導方法に注意しなければならない事項が出るかもしれませんので注視して行きたいと思います。 【今後の検討課題】 1、自転車運転者講習制度の在り方について 本報告書の中でも言及されているが、自転車を交通反則通告制度の対象とするに当たっては、制度の対象外となる16歳未満の者に対する交通安全教育が非常に重要となってくる。今回の提言においては、現時点において自転車運...